今日、とある料理本(わりと初心者用)を読んでいたら、
「料理に使う菜箸(さいばし)のヒモは、切って使う」
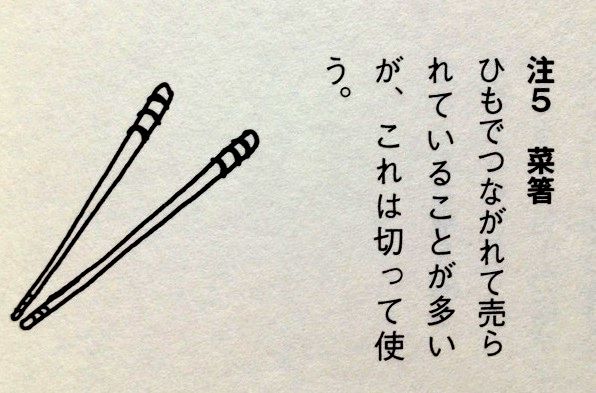
との記述を目にしました。※常識いらずのお料理入門より
さいばしって、アレですよね。
ああ、これこれ。

料理をかき混ぜたりするときに使う、長っちょろい、箸の王様みたいな箸ですよね。
つまり、
キング・オブ・箸 = 菜箸(さいばし)
多分にもれず、ウチにもあります。
確かに、さいばしは購入当初、ヒモで繋がれているときが多いです。
ヒモが付いていると使いにくいので、私はいつも買ってすぐにぶった切っていましたが、
お料理本にも「切って使う」と書いてあるので間違ってなかった!
……と、一瞬思ったのですが。
「では何故、さいばしの販売業者はわざわざコストをかけてまで、2本の箸を紐でくくったのか?」
という疑問が沸きました。
どうせ切られる運命なら、最初から紐なんてつけなければいいですもんね。
どうせ別れる運命なら最初から好きにならなければよかった、みたいな感じですね。
そんなこんなで、ちょっと気になったので「さいばしがヒモでつながれている理由」を、自分なりに調べてみたところ……
さいばし業者が、さいばしにヒモをつけている理由は大きくわけて2つあるとのこと。
さいばしがヒモでつながれている理由その①
さいばしをぶら下げる為
お料理中に、壁にブラッとひっかけて、サッサッサッと使う人もいるので、その為に紐がついている、との説。
また、壁につるしてひっかけてぶら下げておけば、乾かしやすくて衛生的との声も。
さいばしがヒモでつながれている理由その②
無くさないようにする為
バラバラのままだと、無くしてしまうから紐でくくった、との説。
ああ、確かに。
ふたつセットのものって、しょっちゅう無くなりますもんね。
靴下とか……。
紐でくくっとけば、無くすときも一緒、
一心同体、生涯を共にって感じですね。
うーん。
こうして見てみると、最終的にさいばしのヒモは切っても切らなくても、それぞれにメリット・デメリットが存在していると気づけます。
「切るべきか、切らないべきか……」悩ましいですね。
少しでも箸の稼動域をあげて使いやすくするためは、ヒモを切ったほうが良さそう。
つまるところ、菜箸の紐を切るor切らないは、個人の好みで決めてしまっていいと思われます。
「料理の雑学」関連記事





